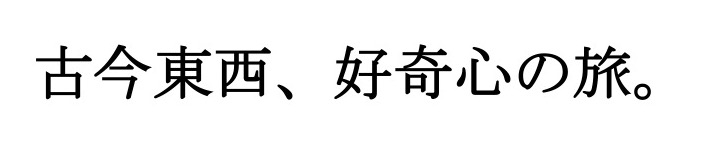【BOOK】静かなる姫、荒ぶる姫。

ルチャ・リブロでオススメされた二冊の姫マンガ。
『死者の書』と『アンダルシア姫』。どちらも冥界と現世の結接点となる姫の物語である。
一言で言うと、「好きだな、この世界観。」
アンダルシア姫 1
アンダルシア姫であるオリベは、スペインを舞台としたアンダルシア地方の大地そのものと繋がりを持つ不思議な力を持った気さくな姫で、2体の鈍臭い機械人形の従者とともに荒れた古城に暮らしている。物語は、日本から来た売れない画家の時蔵がひまわり畑でアンダルシア姫と出会うところから始まる。様々な人間が歴史の積み重ねの中で染み付いて来た執念や怨念、忘れられない情念や無念、欺瞞などの醜い部分を異界の魔物が代弁し、それらを人間の当事者として等身大に受け止め向き合う時蔵と、そんな時蔵を助け魔物をシニカルに制裁し、時に浄化するアンダルシア姫の短編集。一つ一つの魔物事件の奥底に眠る人々の想いの強さは、良いとか、悪いとかではなく、ただただ切ない。愛憎であれ、郷愁であれ、強すぎる想いがひとを縛りつけ、身動きを取れなくしてしまう。その時のつらさ、切なさが、作品の中でエネルギーとして描かれ、それらがグロテスクすぎず、またスマートな形ではないかもしれないが、オリベによって断ち切られて解放されていく。面白いのは、南スペインという歴史的にも複雑な経緯を持つ舞台を選んだことで、作中にもあるけれど「メスキータには、キリスト教徒に再征服されたイスラム教徒の憎しみが渦巻いている」などと歴史の中で積み上げられた人間の性と、現代人の軽はずみな性をうまく時蔵という依り代が結びつけられているところではないかと思う。その結果、アンダルシアの歴史のことを言っているようで、現代人のしがらみを指しているようにも思える。このダークながら、痛快な道徳的ファンタジーの独特な空気感は、夢枕さんの『陰陽師』とも似ていて引き込まれる。
あーーーー、メスキータに行きたい。メスキータに行きたい。前回、うっかりコルドバが行程に入っていると思い込んでいたからなあ。
死者の書 上
こちらは奈良の歴史に関心がある人ならほとんど知っていると言われる折口信夫の「死者の書」を近藤ようこさんが漫画にしたもの。物語の主人公は藤原南家族長 藤原豊成の第一娘子「中将姫」が、二上山に埋められている「死者」大津皇子(滋賀津彦)の死後も想いびとを想う魂に呼応して出会う話。『死者の書』の舞台は当麻寺を麓にもつ二上山である。ここは日本のミステリーが数多く残る葛城や吉野や熊野などの山岳地帯のうちの二上山(ふたかみやま)で、大津皇子伝承や中将姫伝説がのこっている所である。これらに取材し、古代の伝承などを踏まえて作られた物語なのであるが、原作を読んでも文章が独特でなかなかつかみどころがない。うーん、困ったな、と思っていた時に紹介してもらった本がこの漫画版の解釈本である。
「平城京の都の栄える頃のことである。春の彼岸の中日、二上山に日が落ちたとき中将姫は尊い俤びとの姿を見た。父からもらった称讃浄土教を千部写経する願掛けの成就に導かれ、非業の死を遂げた大津皇子の亡霊とまみえる。姫は尊い俤びとと重なるその姿を受けて、蓮糸で曼荼羅に織り上げることでその魂を鎮めるが、自らの魂も浄土へといざなわれていく。」というのが、大まかな話の流れである。この「死者の書」で描かれている中将姫は、14歳の時に継母から殺害を命じされた家臣が殺められずに姫を雲雀山青蓮寺に隠した後に、1年後父親の豊成に見つけられて連れ戻された後からのストーリーのようだ。
『死者の書』というだけあって、ストーリーは冥界や浄土にまつわる静かで厳かな内容で、「中将姫」である郎女(いらつめ)は、アンダルシア姫に比較すると静かな信念をもつ才知に富んだ姫だ。どんな状況にもうろたえることはなく、仏の導きに素直で、凛としている佇まいである。これも大和の地の歴史の積み重ねから来る人間の情念や思いを受けた、深い物語だ。
このどちらの本においても、「姫」の位置付けがあの世とこの世の結節点であり、魂の浄化の象徴であるというところが惹かれる。借りられる本は最大3冊までだったので、早く下巻と続きが読みたいものだとウズウズしている。