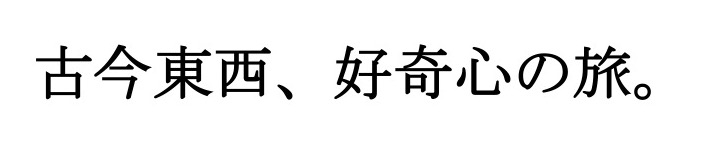フロンティアに生きる街、大阪
商人(あきんど)の街、大阪は、古くから八十島の水都と評されてきた。しか し、実際に訪れると、かねがね聞いていたはずの「島」は見あたらず、すみずみ までまるで「街」のようなふりをして気取っている。その「嘘っぽさ」に、私は 自分の足で踏み歩いてみるまで全く気がつかなかった。
というのも、子供のときから思ってきた「島」という言葉に、絶海の孤島や楽 園の遠い島、といったイメージはあっても、「卑近な繁華街のざわめき」はどう も結びつかなかったからだ。しかし、地図に落として見たらよくわかる。たしか に大阪は島のつながった水の都である。
こうしてフィールドウォークをして大阪が「本当に」「水の都」であることを理 解してからも、自分がそれまで「大阪」だと信じていた土地の半分以上が、⻑い 歴史の中で人々によって開拓され、埋め立てられ、陸地になっていった島の集大 成にすぎないことを思い知らされた。大阪は、まさに古代から水に生かされ、水 と戦ってきた、人と交易の関係性の積み重ねの中で花開いた商いの土地なのだ と。そんな場所を開拓してきた先人たちの苦労といったら、気が知れない。
そしてその大阪の歴史を支えてきたのもまたフロンティアに生きる人々なの だ。彼らは⻄の大陸からの新しい勢力に追われ、遥か彼方のシルクロードの果て の日本まで流れ着いた、いわば高貴な血を持つ亡命者で、未開拓の大阪の島々 に、住まいを作り、氏族の復活と新しい文化を作ることに心血を注いできた。
こうした島の周りが徐々に埋められ、いくつもの島が合わさり、大体、江戶の ころに近代の大阪のかたちができたといわれる。なかでも賑わったのが、四ツ橋 を中心とした船場・島之内・新町・堀江の繁華街エリアである。これらは、江戶 初期に縦の「筋」と横の「通り」で人の手によって作られ、人の手によって区切 られた碁盤目状の商業地であり、上から見れば納得すると思うが、その土地の規 則性は現代にもそのまま引き継がれている。
そして、高麗橋、⻑堀橋、鰹橋、白髪橋、土佐堀、横堀、道頓堀。この界隈を歩 くと、かならず水路にちなんだ楽しい地名に出くわす。新しい堀、なくなった堀。 新しい橋、なくなった橋。あっちにもこっちにもある。近松門左衛門が「名残の 橋づくし」で数えあげているように、堀や川、それに掛かる橋は、大阪に生きる
町人にとって日常と非日常すべての基点となる大切な指標だった。そしてそれ が地名に、高低差に、碁盤目状に整えられた道に今も息づいている。唯一、最初 からなかった橋といったら、そう「あべの橋」だ。あれは、最初からなかった橋 のくせに、大きな顔をして駅名になっている。ちなみに、「はし」ではなく「ば し」。「ほり」ではなく「ぼり」と、濁るのが上方流だ。
そんな大阪を、腰を据えて歩いてみる。(いや、据えたら歩けないのだが。)橋 の向こうに見える島からの川風は心なしか塩っぽく、ぺたぺた肌に張り付いて くる。そう、海が近いのだ。⻑堀橋から土佐稲荷神社を抜けて土手を九条の方向 に、首筋を伝う冷たい汗を何度も感じながら、とにかくずんずん歩いていった。
日本の多くの都市がそうであるように、大阪も昔の面影はないといわれている が、どうも私にはそうは思えなかった。なんの目新しさもない、車の波が絶えな い騒々しいばかりの場所にさみしく取り残された石碑や跡地ばかりだが、私は それで満足だった。難波のお洒落スポット「堀江」さえも、川沿いは人気のない 寂れた倉庫街で、戦火で煤けた古い建物が続いていたり、自転車に全財産を積ん だ気難しい爺さんがこちらを「ぎょろり」とみていたりする。橋の先の松島では、 花街の艶やかさの中にぴりっと張り詰めた視線が刺さるのを感じる。そんな歴 史や暮らしにグルグル思いを馳せると、気取りのない、水辺の大阪の姿が生き生 きと浮かび上がってくる。
街のはずれの海へ向かい、行き交うサラリーマンや OL の数がどんどん減って いく中で、一体どれだけの時間、歩いただろうか。淀屋橋からひたすら⻄にむか い、⻑堀橋を超え、新町を木津川の伯楽橋を通り過ぎ、花街の松島新地の結界に 足を踏み入れ、その妖艶で閉鎖的な空気に当てられながら、ようやく⻄九条にた どりついた時には、あれだけ根気よく残っていた太陽が、もう見えなくなりそう になっていた。名前も知らない小さな工場の多い川岸の片隅の空き地に、まるで 歴史に忘れ去られたかのように、河村瑞賢の顕彰碑が佇んでいた。その静かな石 碑の後ろからは、薄いオレンジ色の⻄日が粒のようにキラキラとこぼれていた。 そうだ、私はこの目でこれを見たかったのだ。これが、かつて「よそ者が生きる ため」に大阪の水辺に戦いを挑んできたイノベーティブな場所であった。
人も歴 史も商いも、いつだってフロンティアが熱いのだ。それが水都・大阪だ。