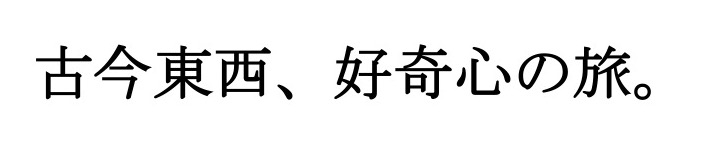世界のもう半分から見た歴史と今 (後編)
ずーっと前に話させてもらったイベントの資料としてまとめたメモ。アーカイブと備忘録的にブログに残しています。
(前編はこちら)
世界のもう半分から見た歴史と今 (前編)
こちらは、後編となります。
目次
1.ヨーロッパ産業革命とイスラーム交易の衰退
・スペイン・ポルトガルの新大陸発見後、世界は一つにつながった。
→世界の一体化、大規模なグローバル分業体制を意味する「世界システム」の成立
(新大陸の植物をヨーロッパ大陸で生産、ヨーロッパ大陸のものを新大陸で生産)
ex)じゃがいも、トマト、トウモロコシなど ex) サトウキビなど
→地球の全てを見つけたことで分業体制の限界を迎えてしまった。(搾取の限界)
→新大陸で発見した植物のヨーロッパ伝播(人口増大)と、ヨーロッパが必要な世界
商品の新大陸での育成(コロンブスの交換)=プランテーション化
→絶対王政の中での封建的生産関係の経済の限界。
→1620年代からの停滞へ。
→官僚制度と常備軍の高い財政負担。奢侈的宮廷派と重い租税に喘ぐ地方派
→反乱や暴動につながる。
*社会基盤をなす生産関係を、近代的・資本主義的なものに変換するしか打開できない。
(生産関係の激変=革命、ブルジョワ(市民)革命→イギリスの成功)
↓
農業革命でもなく、植物依存から鉱物資源への転向をするわけでもなく、 プランテーションを拡大し、貿易関係を世界に広げることにより果たした。
=奴隷貿易を基軸とする環太平洋ネットワークの中心にイギリスが座る。
=世界的商業の主導権を押さえる
↓
イギリスが世界の覇権を制す(17世紀後半からオランダ・フランスを撃破)
→オランダに次ぐヘゲモニー国家(覇権国家)となる。
*ヘゲモニーを確立した国はイデオロギー的にも必然的に自由貿易を主張。
アメリカが自由貿易、より広義では自由主義の使者であったのはそのヘゲモニーが確固としている間だけ。(圧倒的な経済力で、他諸国を圧倒できる最も安上がりな方法だから。それに反して王政・帝政はその妨げとなるから、ヘゲモニー国家はのちに支配国にビジネスと政治介入的な意図で独立・民主化を促進。)
*貿易商は東インド会社などで儲けたその裕福さから、本来の貴族のジェントルマンの仲間入りへ。(成金)
→ロンドンやブリストルの港町が発展(オランダと同じく生産→商業(港)→金融)
→金の相場を未だにロンドンで決めているのはこの時の名残。
*ヨーロッパとアジア・アメリカをつなぐ交易リンクが出来上がり、イギリスがその主導権を握ったために、世界中の人々が生産したものを最も安価で手に入れることが可能になった。
*商業革命の展開に伴い、ヨーロッパにアジアやアメリカの新奇な商品が流入。
→ここからヨーロッパ人の生活が一変(イギリス人の綿織物と紅茶の普及)
=近代ヨーロッパの生活様式が確立=生活必需品となったアジア商品の国産化
=工業化の進行(産業革命)=交通・生活様式の都市化、近代への変化
(満員電車で定時に通勤、集合労働、チェーン店でいつでもどこでもコーヒーとパンを簡易に食事、という現在の生活スタイルが生まれる)
=大量生産・大量消費時代の幕開け(イギリスを中心としたヨーロッパ経済の飛躍)
=既存のシルクロードを生かした交易構造からの転換
*モスクの代わりとなったコーヒーハウス(市民のための情報・議論の場)
イギリスで最初のコーヒーハウスは1650年のオクスフォード
→身分や経済力の違いを気にしない「自由」の雰囲気の元に、友好を温め、情報交換をし、互いに批判しあい、議論し合う。
→近代文化の誕生を促進
(科学の王立協会、新聞や雑誌のジャーナリズム、イングランド銀行の設立、株情報から証券会社や銀行・保険会社の設立、党派の誕生、文学(小説)・芝居・音楽など)
=アッバース朝・ササン朝と同じく繁栄。
=文化混交のネットワークを築く通商インフラを制する者が繁栄する。
=ただし、混交は異民族間ではなく、国内のヒエラルキー間で行われた
【参考】キャラバンサライ(隊商宿)
イスラームにとっての交易インフラ ダマスカス・バクダッド・アンダルシアとイスラム文明発展や爛熟の足跡を支えたのがイスラームの「交易」という共存共栄のシステムであったことは、前回の通り。その重要な背景となったのがキャラバンサライ(隊商宿)という貿易ルート(シルクロード)に置かれ拠点の整備である。
イスラム預言者ムハンマドが青年時代の仕事が隊商であったことから、隊商を通じて各地の様子を知り、やがてイスラムの教えを感得したように、隊商は商品を東西に流通させるだけでなく、土地の文化をまた別の土地に伝え、新たな形で開花させた。それらを支えたインフラがキャラバンサライである。トルコでは「ハーン」、アラブ世界では「フンドゥク」と呼ばれた。ここから都市や農村で生産される商品が地域を超えて活発に取引されるようになり、陸路や海上ルートが、大都市を中心に広範囲に確立され、イスラム経済を栄えさせた。それに伴い、商業活動からイスラームに帰依していく遊牧民部族地域が増えていった(インドネシアやインドなど)
=イスラームに見られる相互扶助の精神は、絶え間ないキャラバンによる貿易活動と キャラバンサライの機能によって強められた。宗教も民族も気にせず、異邦人を親切に温かく迎え入れるムスリムの心情は、砂漠や移動の文化から培われていった。
=気候条件の厳しい場所での過酷な旅をするイスラーム世界ならではの人を助ける精神 「人を助ければ助けるほど自分が助かる」
=イスラーム為政者も経済発展による恩恵を個々の平民に与えなければ「正義」から逸脱したものとして見られるので、キャラバンサライやそれにまつわるバザール・モスク・メドレセ・カレーズ(水路)などの文化事業に力をいれて還元する(利益分配)
=神の前の平等(ゆるい民主主義)
→19世紀のイギリスを中心とした交通(蒸気)と生産の近代化(プランテーション・大量生産化・工業化)による経済構造変化と、西欧がもたらした国民国家システム(国家間の経済競争に生き残るための強い結束力を求めるもの)により、中東世界にこれまでになかった「国境」という西欧都合の人為的垣根が作られ、人々の往来と交流が不自由になり、異民族・異宗教のアイデンティティの決別が生まれていく。
→その後の中東の混乱と相互不和の火種となる(西欧システムに合わない歪みの結末)
2. 第一次・第二次世界大戦と世界秩序の再編
・オスマントルコ帝国の衰退
生産力の工場はヨーロッパの国々にさらなる原料と新たな市場を求めさせたが、 すでにアメリカ、アフリカ、アジアは手中にあった。
→地理的に近い中東からアナログに作った原料を輸入し、生産加工して大量に輸出。 (中東を輸入国から輸出(消費国)へシフトさせる)
→中東の貿易収支の急激な悪化
→400年にわたるオスマンの統治機構の疲弊 (近代化を遂げるための資本も統率力のある派閥もなし(多派閥の共存のため))
→輸入でヨーロッパから借金を始め、それが雪だるま式に増大し財政破綻を引き起こす
→オスマン傘下のイスラーム諸国も同じ運命に
→イギリス・フランスなどのヨーロッパの経済・政治介入と支配を許す 「ヨーロッパの瀕死の病人」と呼ばれていく
→ロシアの影響力(バルカン半島を狙うロシアと露土戦争。ロシアがオスマン配下の異宗教の小国をそそのかしギリシャなどを独立させる)
クリミア戦争の出費と疲弊で末期症状に。帝国内の分離独立を目指すキリスト教圏のナショナリズム高揚にて、他国からの武器供与と、単一民族国家作成のためのユダヤ人やムスリムの虐殺(民族浄化)。 (ミッレト制でうまく共存していたにもかかわらず、ヨーロッパがナショナリズムを煽ったことで、以後の払拭できない程の敵対感情をムスリムとキリスト教間にもたらした)
→トルコナショナリズムを目指した青年トルコ党が、従来のしがらみを打ち切り、帝国の近代化を目指し、再起をかけた独裁化を進めてドイツに接近。
→第一次世界大戦でドイツ・オスマントルコ敗戦。
世界から「帝国」の消滅。
→ヨーロッパ統治の本格化
→現地民の激しい暴動(ジハード)
→欧米は武力弾圧の上、親独裁者を据える(中東の独裁政権と対立を作ったのは欧米)
第一次大戦時とサイクス・ピコ協定による人工国家
サイクス・ピコ協定
イギリスの外交顧問マーク・サイクス卿、フランスの外交官フランソワ・ジョルジュ・ピコにロシアの外交官サイゾフが加わり、第一次世界大戦時にオスマン帝国の分割案としてペトログラードにて結ばれた秘密協定。(かわいそうなロシアは協定名に入れてもらえず)
→不自然にまっすぐな国境線で分断された中東(人工国家の設立)。
→インドに植民地を持つイギリスは東のイラク地帯を、レヴァントに拠点があるフランスは西のシリア・レバノンを、黒海を確保したロシアはボスフォラス・ダーダルネスをめ、三ヶ国で中東を分配。
=この境界線がのちの100年の世界情勢を揺るがす元凶となる
=イギリスは更にアラブ人の国家独立(フサイン・マクマモン協定)と、パレスチナにおけるユダヤ人居留地の建設(バルフォア宣言)の約束も平行して行なっており、三枚舌外交と呼ばれる。
・イラクとイギリス
旧オスマン帝国でのモースル、バクダード、バスラ州が政治拠点に。
→オスマントルコ配下で雇用されていたスンニ派の教育者や法学者、将校の失業。
→シーア派の聖職者たちもイギリスの占領に抵抗、独立を求めるように。(スンニ派とシーア派の協業)アブダッラーのイラク国王を名乗る。
→イギリスは国際連盟からの委任統治の権限があるという口実で独立を許さず。
→イギリスは解放者の立場できたし、多少民族配慮もしたものの、結果的には敵視される立場に。
・シリアとフランス
→委任統治領であることを口実に、アブダッラーの弟のシリア王ファイサルに対し独立を認めず、委任統治を認めるように圧力をかける
→拒絶を求める国民と、フランスの実力を知るファイサルは即断できず。
→反フランス勢力が瞬く間に広がり、フランス・シリア戦争と呼ばれるほどの規模の 暴動に。フランスは圧倒的火力でダマスカスを占領。
ファイサルはイギリスへ亡命。
→イギリスは自分が監視するアラブ人統治を目指すため、ファイサルをイラク王への即位を認める。1920年には占領統治の終結も宣言。ファイサルが手駒になることを期待したが、これが見込違いに民衆の反感を買う。(多くのイラク人がファイサルを「よそ者」とみなしたこと、スンニ派であることから シーア派のムスリムから支持を得られなかった。)
エジプトにフランスがスエズ運河を開拓するも、財政難に陥ったエジプトがイギリスへ権利を売却。軍事侵攻でイギリスの支配下にされてしまう。
→煮え湯を飲んだフランスは、奪還を試みるもうまくいかず、周辺地域のレヴァントの支配を試みる。
→シリア西部のダマスカス・ヒムス・ハマー・アレッポを結ぶ重要地域を握る
→そこにシリア、またシリアから切り取ったレバノン(マロン派キリスト教徒の国)という人口国家を作り上げる。シリアは半フランス機運が急速に高まる。 →シリアは地方行政もフランスがとりしきり、遊牧民をシリア北部に定住することを強要。クルド人など。
→フランス・シリア戦争へ。フランスはシリアと融和の道を模索するが、圧倒的多数のスンニ派ではなく、異教とされているアラウィー派などの少数派を優遇。(アラウィー派がシーア派というのはアサド政権での後付け)国内の不満分子が増加。
第二世界大戦とイラン
→ナチス・ドイツとペルシアの協力関係(どちらも元々アーリア人)
ドイツは対ソビエトとしてイラン内に諜報網を築く
→イギリスとソ連がペルシアからドイツの追放を要請。親独のレザー・シャーは退位
→第二次世界大戦時にイギリス・ソ連の対抗勢力としてアメリカに近づく。
→大戦後のアメリカの影響力が残るが、イラン国内では国内の混乱と戦時下のインフレで外国全てを排斥する民族主義が広がりつつあった。
→石油会社の国有化を目指すが、イギリスや米国によりモサッテグ政権が潰される
→石油会社の権益を米英で二分。富裕層には欧米文化が普及し、国民の反感を買う。
→1979年 反米性格が強い革命が起こり、イラン・イスラム共和国が樹立 ・サウジアラビア(サウード家の王国)
→貧しいベドウィンの国から石油発掘で一躍オイル・ダラーへ。
→欧米各国の熱い視線が注ぐ
→第二次世界大戦においてサウジアラビアは中立といったものの、米英からの資金でドイツに宣戦布告。米英は中東の盟主となること期待するも、混乱を避けたいサウジは動かず。再びアメリカに近づいたのは、ヨルダンとイラクを支配していたハーシム家(親英)の軍隊に脅かされるようになってから。
3.戦後のイスラーム諸国の混乱と分離
・東西両陣営の対決、競合する冷戦の時代へ
・米国を中心とする資本主義陣営はオリエントに眠る石油という膨大なエネルギー確保に躍起となり、謀略を巡らし、意のままに操れる体制を後押しし、その国内の人権抑圧には目をつぶっていた。利権のために大量の武器供与も行い、それがさらなる混乱に拍車をかけ、多くの人命を奪った。
・手段を選ばず国益を追求する欧米の意図が「殺しあうオリエント」をもたらす。
エドワード・サイード(パレスチナ系米国人・批評家)
「歴史とは人間が作るものであり、作らずに置くことも、書き直すことも可能だ」 著書:オリエンタリズム(2003) 「オリエント」という半ば神話的概念は18世紀末にナポレオンがエジプトを侵略して以来、作られてはまた作り直されるということを無数に繰り返してきたのだ。その過程で、これがオリエントの本質であり、それゆえそれにふさわしいように扱ってやらなければならないのだと便宜的な正確の知識を通じて断定しようとする権力によって数え切れない歴史の堆積物、そこに含まれる数知れぬ歴史と目もくらむほど多種多様な民族・言葉・経験・文化などはすべて履き捨てられ、無視されt、バクダッドから略奪された宝物の、粉々に粉砕され無意味になった破片と一緒くたにして砂の山に葬り去られている。
→「オリエンタリズム」とは欧米が作り出した中東蔑視のために生み出された概念。 「多数のアイデンティティをもつという足場の定まらない感覚を、私は生涯持ち続け てきた。それに付随して鮮明に記憶されているのは、私たちが完全なアラブであるか、さもなくば完全な欧米人であったらよかったのに、完全な正教会派キリスト教か、完全なムスリムか、完全なエジプト人であったらよかったのにという絶望的な感情を抱いていたことである。 ーハーバード大卒で、アラビア語と英語を話し、キリスト教を信じるパレスチナ人の両親を持ち、姓はアラブ系でありながら、名前はイギリスに由来するサイードの心情は、今の蔑視と迫害のイメージを持たれる孤独なイスラム系移民2世・3世にも通じる。そして、そんな彼らを格好の標的とするのが宗教という名の隠れ蓑を背負った過激派テロ組織だった。
4.世界におけるイスラームの変化と今後
・第二次世界大戦後のイギリスの財政難による植民地放棄
→パレスチナの放置、インド、パキスタンの分離独立、エジプトのスエズ運河の放棄
→これに変わって資本主義陣営として中東に台頭していくのがアメリカ
→トルーマンドクトリンなどで独裁政権下の共産主義の浸透を阻止することを目指す (中国の二の舞にならないため)
→米国主導の軍事条約はアラブ・ナショナリズムと衝突し、エジプト・シリア・ヨルダンなどとの関係性が悪化。共産化を進めたいロシアとの拮抗の中で各地の宗教派閥の紛争が、欧米の代理戦争となっていく。
*「イスラム過激派」によるとされる反米テロは、ブローバック(しっぺ返し)現象の一つと言われている。
ブローバック現象
戦争や政権転覆の工作など、米国政府が行った行為に対する反応で、米国の被害者となった人々に払拭できない記憶や憤慨として残る。対テロ戦争でアフガンやイラクで犠牲になった人々の家族は米国の理不尽な武力行使を忘れず、米国は第二次産業革命時から継続している戦争産業によってテロの種子を世界中に巻いている。
アイゼンハワー大統領 「軍産複合体の不当な影響力に対して、米国は自らを守らなければならない」
→しかしアメリカは耳を貸さず、ベトナム戦争、アフガン戦争、イラク戦争と大義ない泥沼戦争の中で戦争赤字を生み出す。
・第三次中東戦争でのイスラエルの圧倒的な勝利 (欧米において経済的地位が高く発言権のあるユダヤ人の影響力と支援)
→アラブ国家はユダヤ・キリスト教同盟がイスラム諸国を侵食していると認識。
サウジアラビアのアブドゥル・アズィーズ(ファハド国王) 「ムスリムはパレスチナの地がイスラムに戻されるまでジハードをしなければならない。
エドワード・サイード「イスラム報道」
「私はムスリムがイスラムの名によってイスラエル人や西洋人を攻撃したり傷つけたりしたことがない、などと言っているわけではない。私が語っているのは、人がイスラムについて(欧米の)メディアを通して読んだり、見たりすることのほとんどが、暴力行為はイスラムに由来するものであり、「イスラム」とはそういうものだからだ、と伝えられている、ということである。その結果、イスラム地域で発生する具体的で、正確な様々な状況は意識されないか、無視される。言い換えれば、世界でイスラムについて報道するということは、ムスリム(イスラム教徒)が何しているかを曖昧にする一方で、このように「欠陥だらけ」と伝えられるムスリムやアラブ人とは何者であるかが強調される一面的な行為担っている。(宮田律加筆・修正)
*フランスのパレスチナ(アラブ)容認姿勢
→シャルリ・エブド事件・・ムハンマドの風刺画による襲撃
→パリでのテロ発生 →市民のデモ行進(表現の自由・博愛の精神の強調)
→フランス人口の約1割はアラブ系住民であることを踏まえた中東和平イニシアチブ
*2016年ロンドン市長選 野党労働党議員でイスラム教とのサディク・カーン氏が当選(イスラムフォビアが台頭する中でのロンドン市民の政治・文化意識の多様性)
4.現代のキャラバンの可能性
→現代の情報ツールを駆使し、二世・三世として宗教からも一歩引いた世界の若者たちが価値観を共有し、ヨーロッパ植民地主義が作り上げた国境を超えて交流していけば世界情勢のさらなる構造変化が期待できるかもしれない。
それらはかつての物資とともに人の価値観を運んだ隊商を彷彿とさせる。
あとは、それらを担うインフラのキャラバンサライを「だれ」と「何」が「どの規模」で担うか。