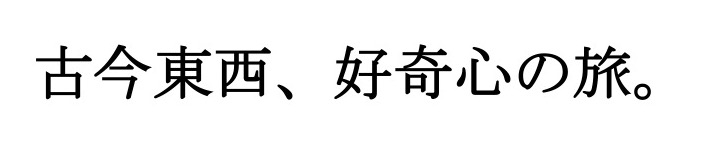【Book】現代の地政学
歴史が好きで、民族学が好きで、地図が好きで、文化が好きで、自分の足で確かめるのが好きで、その他いろいろ好きすぎて、調べたがり。
そんな私には非常にありがたい私設図書館ルチャ・リブロが隣町にあるのだが、そこで借りた「現代の地政学」という本が面白かった。
地政学がらみの本は、川北さんの「世界システム論講義」や曽村さんの「地政学入門」などを読んだのが始まりだったが、改めて検索してみると地政学がらみの本が出るわ出るわで、関心度が高いトピックスというのがわかる。が、そのぶん良い本というのも選別しなきゃいけなくて悩ましい。そこで私が入門編として読みやすかった良本を参考までにご紹介したのが、先ほどの2冊だった。特に曽村さんの「地政学入門」は本当にわかりやすく地政学のものの見方を書いてくれている。今回の佐藤さんのこの本も、一つの見方として示唆に富んだものだと感じた。
全体的な内容は、ただもうひたすら「自分で考える材料集めとして、読んだら面白いよ」と思うだけなので、書評というよりは、それぞれのトピックスに対する所感というか、頭によぎったことを書いてみたい。
ところで、最近は本を読むときには「著者がどういう背景とタイミングから、どういう視点で書いているのか?」を意識するようにしている。この方の本は初めて読んだのだが、ロシアになんか特別な思い入れがあるのかなと思ったので、プロフィールを読んだところ「ああ、専門家か。」と納得した。また、宗教と政治に置いてどこに対しても客観的で等距離のバランスを保っていそうに見えて、それでいて「この方クリスチャンなのかな?」と思わせるようなキリスト教寄りの記述が節々にあった。こちらはプロフィールではわからなかった。私が中高と真宗大谷派の学校に通っていて、大学で少しの間イスラーム圏に住んでいたことから、仏教・イスラームを探求してからキリスト教、ユダヤ教へと興味の対象を広げて行ったこともあって、うまく言えないのだが書き方の微妙なニュアンスを肌で感じやすいのだ(だからどうということは無いのだが)。
以下、いくつか面白かったトピックスについて書いて見る。
目次
地政学の地理のキモは地上の山岳地帯、目に見えないキモは宗教と人種。
ここに山があって、こういう地形になっていて、歴史的(宗教的にも)にこういう経緯があるというのを一枚の地図から読み取れる力があるかどうか。それが重要である。
これは「確かに!」と思った。
「地上の山岳地帯」というのは、今の立体的な戦い(陸海空)でも昔の平面的な戦い(陸海)でも変わらない。山というのは非常に怖くて、どこに崖があって川があって洞穴があって、などの土地勘のあるものでなければ遭難や怪我をしやすい。そして何より空からも陸からも見つけづらいし、ゲリラ攻撃もされやすい。さらに急峻な山々であればあるほど、そのゲリラ攻撃に対抗するだけの大規模な戦力や兵器を持ち込むこともできない。山という存在自体で物理的なアクセスも遮断されるし、電波も入りづらい。
なぜアメリカはアフガニスタンを平定できなかったのか。これはアフガニスタンという国の地形がほとんど山だと言っていいからです。なぜアメリカはイラク戦で失敗したのか。それはイラクの一部が山だからです。なぜチェチェン紛争でロシアがあんなに大変だったのか。今もチェチェンはカディロフ政権がプーチンのいうことをほとんど聞かない状態となっています。どうしてでしょうか。それはチェチェンが山だからです。なぜスイスが永世中立国で、金融の中心国家として自らを位置付けられるかと言えば、それはスイスが山だからです。要するに一言で言えば、「“山”の周辺地域を巨大な帝国が制圧して、自らの影響下に入れることは難しい」という、このマッキンダーの地政学的な制約要件は、現在も生きているということです。(中略)だからわれわれは地図を見るときは平面で見るけれど、立体で地図を見て見る努力をするべきである。山があるということは大変な障害の原因になるし、トラブルは山から生じる。
そう考えると、「国を持たない最大の民族」と呼ばれるクルド人の問題についても、彼らが住んでいるのはトルコ・イラク・イランをまたがる山岳地帯だ。
「宗教」というものは信者がいないと成り立たないものであり、かつ一つではない(たくさん種類がある)。そうすると、維持するためには自然と信者を増やす必要が出てきて、そのためには勢力拡大と利権の争いがどうしても絡んでくる。その結果、力をつけた宗教は一つの共同体となり、指導者は権力を手に入れ、それを維持し拡大するためのコミュニティ=国を作る。人の心に訴えかけるものであるからこそ、宗教というのは広がりやすく、結果的に支配や力の誇示、植民地化の材料として用いられる。だから、本来的に宗教と政治と金を歴史から切り離して考えることは難しい。
「人種」は、さらにセンシティブであり、国境線という概念が生まれる前に人々が移動をしたり出稼ぎに行ったりしながら混じり合っていることがデフォルトの状態だ。さらに、ヒエラルキーにおける上位の支配階層が下層の労働階層に対して不満を抑制するべく、さらに下層の位置付けを作る際に少数の人種や民族が用いられることがある。また、そういったことがなくても少数の人種や民族は多数派の中で区別され、生きづらいことが多い。それらも潜在的なテロリズムの火種となりうる。ミャンマーのイスラーム少数民族ロヒンギャの難民問題は、その最たるものだと思う。
直接関係はないがふと感じたのが、宗教もまた山や丘の関係が深いということだ。お寺があるのも山であることが多いし、キリストはゴルゴダの丘で、イスラームはアラファト山、釈迦は須弥山(これは実在しないが)。
地政学とファシズム
話の中身としては、難民問題に直面する欧州で、各国が「難民が世話になりたくない、住みにくいと思うような国になりたい」としてファシズムが働く動きにあるということ。例えば、ドイツへの難民受け入れによってネオナチの活動と外国人排斥運動の報道が増え、活発化したように見えること。それらの国の内向きのポージングによって、難民を怖がらせて入国を抑制しようとする動きが影にあるように見えるということ。
また、アルバニアなどの国家が破綻していて情勢が不安定な国は難民が近寄らない。そうすると、飽和して行き先を失った難民を保護するために、日本にも受け入れの圧力が国際的にかかることになり、欧米が日本の支援金で手配した航空券を難民に渡し、彼らが経由地の日本の空港に立てこもることでなし崩し的に受け入れざるを得ない状況に追い込まれる可能性があるということ。そういった難民の中には、不遇の環境からテロリストとなった者がいる可能性もあるし、あるいは難民としての生活苦や差別、アイデンティティへの悩みから2世・3世としてホームグロウンテロリスト化する可能性もあるということ。
確かにキリスト教・白人・ネーションステートを基調とする「国」でのまとまりが前提である欧米において、難民の大量受け入れによるアイデンティティの希薄化と国内統制の喪失への恐怖はあるように思える。だから、良くも悪くも主張に合致した準備をしつつある各国に対して、日本としても難民を「受け入れる」ならそれなりの国内体制を整える必要があるし、「受け入れない」ならそれ相応の「受け入れられない」物理的な理由や事情を国際的に提示する必要がある。が、どうなることやら。
今後の中東の震源地はサウジアラビア。存在感増すイラン。
近年サウジの影響力が弱まっているように感じる。石油に関しても代替エネルギーが開発され、イランも欧米と協調しながら油田開発を本格再開し、イスラームの宗主国としても、メッカやメディナの聖地巡礼に基づく産業は最近バーチャル化しているし、インターネットの普及でサウジに行かなくてもスンニ派のスタンダードな教義は形式化され諸外国で学ぶこともできる。そして、スンニ派のライバルのシーア派大国のイランがイラク、レバノン、シリアとサウジを囲むように勢力を伸ばしつつある。そういったことから、だんだんアラブの盟主としての発言権が危うくなってきているが、大国のプライドは失えないので協調をしていくこともできない。そうすると「サウード王家のアラビア」という国家の強い統治体制が緩んでくる。アラブの盟主が緩んでくると、、、その先は自明なので言えないが、そうすると中東全体のバランスが大きく崩れることになるので一国だけの問題にはとどまらない。そして忘れてはならないのはイスラームは本来「国境なき緩い共同文化圏」であり、国境があること自体が今まで不自然だったので、一度崩れたら最後二度と同じ形には戻れない。サウジアラビアのバランスを保つことは、そのまま中東と欧米の川の堤防を支えている様なものである。イランという国は元々「ペルシャ帝国」の高度な文明を起こした民というプライドがすごくあって、「エジプトとペルシャの文明を踏み台にして大きくなった様な無文明のベドウィンの国アラビアに屈するぐらいなら、スンニ派の彼らがもっとも嫌がる「シーア派」を国教にしてやる。」という感じでゾロアスター教やネストリウス派キリスト教などからイスラームのシーア派に改宗した経緯があるから(ちょっと極端な書き方をしたが)、サウジとは仲が悪いし、「中東」という括りで一緒にされたくないと思ってる。しかし核開発問題で国際的な圧力や制裁を受けていたことから、なかなか表舞台に出ることができなかった。が、ここにきて協調路線を保っており、テロ掃討にも力を入れて影響力を伸ばし始めている。そのために、本来メジャーであったスンニ派諸国にしては脅威となっている。結果的にサウジがイランの脅威が増して抑止力としてパキスタンから核を買うことになれば、中東のさらなる混乱と見えないテロリズムは免れない。願わくばそういう状態になる前に、イランに行っておこう!というのが私の旅の趣旨である。(そこ!?)
中東の民族形成がされている国、されていない国で明暗が分かれる
これはちょっと違和感を感じるトピックスだった。だいたい「国民国家」という概念は欧米のものなので、イスラーム圏を「国」ありきで考えること自体が無理がある。彼らにとっては、前述した通り「緩い文化共同体」なのだ。それを、欧米が引いた境界線の中で統治がうまく行った国、行かなかった国の評価を「民族形成」できているかどうかで判断することが納得いかない。筆者がトルコとイランは「民族形成がうまく行ってるから安定している」という言い方をしていることはちょっと違っていて、トルコは自分たちで帝国制から共和国化した歴史があり、イランはペルシャ帝国の末裔というアイデンティティがあることから、元々まとまりがあって国が成立している。と言っても、安定している訳ではなく、クルド民族などの少数民族問題の火種は未だに大きな問題として抱えている。
パリが狙われた理由。フランスがイスラム化する?
文中に紹介されていた、ミシェル・ウエルベック『服従』という小説は、部分的にありえそうな話だと思った。
これは近未来を舞台にした小説で、こんなストーリーです。2022年のフランスの大統領選挙の第一次選挙で、一位がファシストの国民戦線になる。二位がムスリム同胞団になる。社会党と保守勢力、元々の共和国連合は三位、四位に甘んじてしまった。こうなるともう選挙の時には内戦や衝突も起きる状態です。そんな状況の中で、フランスの保守派と社会主義者は究極の選択を迫られる。ファシスト政権がいいか、それともイスラム政権がいいかという選択です。
登場人物の一人にベン・アッベスという大統領候補が出てきますが、イランのロウハニ大統領をモデルにしているように私には思えます。ベン・アッベスはファシストがフランスの大統領になることだけは阻止しようとして、社会党も穏健派もベン・アッベスを消極的に支援する。それで、ついにフランスがイスラム化するんですね。でも、イスラム政権も、イスラムの法律であるシャリーアをフランス人に強制したり、女性の労働を禁止したりは一切しません。ただし、「他の制度には何も手をつけない。その代わり教育に関しては全権を握らせてください。」ということで女性の教育や労働に税金をかけ、家にいた方が扶養手当や子供手当が潤沢に出るようにする。大学教授はイスラム教徒でないといけないから、現業の人々は解雇されるけれども別に出版活動や知的活動が制限される訳ではない。しかも大学を勤め上げた時と同じ年金が支給される。こんな風に働かなくてもアラブ諸国からどんどんお金がもらえる社会になってだんだんまったりした雰囲気になってくる。そうしたらフランス国民は次々とイスラム教徒に改宗していく。それでEUがイスラム化していき、地中海沿岸諸国と合わさって新しいイスラム帝国ができていくという話です。(中略)これがベストセラーになるということは、この作品が世の中の空気を敏感に反映しているということです。今、フランスの社会には移民が増えてイスラムが広がっていることに対する諦めと、イスラム的な価値観に対する憧れが潜んでいる。テロリストたちはそこを明らかに読み取っていて、それでフランス社会が分裂する可能性があると踏んだ。
私はこの本は読んでないのだが、説明を読む限りは、アラブからの資金流入はサウジかイランが現実的に豊かで安定していないと考えにくい。あと、イスラームの風習と女性に対する描写がなんだか偏ってるなあ。。。。と個人的には思うが、元々オスマントルコ帝国のゆるーいイスラム統治下にあったヨーロッパ諸国において、行くとこまで行った資本主義の息苦しさから、イスラームの「緩い自治」というのは確かに魅力的に映ることもあると思われる。特に難民や移住者の二世・三世は、自身の生活のアイデンティティとしても惹かれる。そう行った人たちが自由と平等の名の下に立ち上がって、欧米の政権の中に入って行く。そういったプロセスにおいてイスラームに関心を持った人々に対して、本来のイスラームの教えではなく、イスラームの皮をかぶったテロリズムがつけいることは考えられそうだと思った。
上記だけでも「どの視座でどの場所から見るか」によって同じ事象でも感じる見方は色々ある。そう行った普段真剣に考える機会が少ないことに対して、自分の視座から考えを深めて見る材料として読んで見るのには大変有効ではないかと思う。