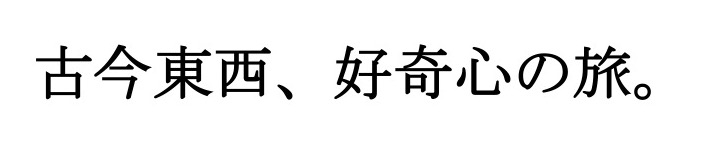【BOOK】ラディカル・ヒストリー 〜民族と宗教のモザイク、ロシア史とイスラム史のフロンティア〜
みなさん、われわれは未来が輝かしいことを知っています。変わり続けるのは過去なのです。
ーある哲学者の言葉ー
近い将来、世界の全ての国々にモスクや礼拝場所が設置され、ヒジャブをおしゃれにまとった女性がハラールの食事を嗜む時代がくるかもしれない。そして、西欧文化の隆盛を下支えしたイスラームの、国境を明確に持たないコミュニティベースの都市交易経済文化が再び世界のスタンダードとして誰もが当たり前のことととして認識する時代が。それを明確に感じたのが、今回のロシアの旅であった。
ウィキペディアによると、
ロシア国内に居住するムスリムの人口は、総人口の15-20%(アメリカ合衆国国務省推計)から、約6%(世論調査機関VTsIOMの2006年調査)と推計される。ムスリムの人口増加率は、ロシア人のものよりも高いため、21世紀半ばには、ロシアの人口の3分の1がムスリムになるという推計も存在する。ーウィキペディア「ロシアにおけるイスラーム」より
とあり、米の調査資料でもムスリムが最も存在するのはもはや中東ではなく、アジアであるとされている。「イスラーム=中東」という固定概念はできる限り速く捨てた方がいい。欧米が記憶の奥底にしまい込んだだけで、今も昔も「イスラーム=(Euro+Asia=ユーラシア=世界)」なのだ。
The Future of the Global Muslim Population
私は今現在ムスリムではないし、何が「正しい」イスラームかにも興味はないし、豚玉焼きが好きなのでこの先もムスリムにはなれないと思うが、この文化の再転換が近づいていることにはものすごく関心がある。定住にこだわらないノマド生活、物をストックするのではなくシェアする生活、利益よりも自分がやりたいことの価値を商いとして追求する生活、近しい価値観の仲間で協業し助け合う生活など、少しずつ少しずつその兆しは見えてきている。今後の本格的な過渡期を迎える時には、資本主義で反映してきた欧米諸国が最後の抵抗として中東戦争を起こすかもしれない。それこそイン・シャー・アッラー(神のみこころのままに)だ。
そんなことを考えさせる、ロシアの中のイスラームとロシアの関係史と、世界最大規模の多民族多宗教国家であるロシアの弾圧と融和と根底にあるコンプレックスについて書かれた書籍が「ラディカル・ヒストリー」である。1991年なので少し古い本だが、当時においてもすでにロシアは世界の中で5番目にムスリムが多い多民族他宗教国家であったので、その考察がとても面白い。
浄土真宗本願寺派法主大谷光瑞は、大谷探検隊を率いて仏蹟調査のため西域探検を行なった(第一次大谷探検隊)。その弟子に橘瑞超という僧侶探検家がいる。彼は第二次、第三次の探検で中央アジアを旅し、さまよえる湖のロプ・ノールや美しい王妃のミイラで有名な楼蘭を発見した人物だ。(このへんの詳しい内容を知りたい人は、東京国立博物館(上野)の東洋館の常設展を見ることをお勧めする。)プロフィールに文字数を取ってしまったが、紹介したいのはその瑞超の言葉であるそうだ。1910年の夏(明治四十三年)、彼はロシア帝国から中国国領に入国しようとしていた時に一人のトルコ系ムスリムに偶然出会った。その後イスラーム世界の広域性に感銘を受けた彼はこのように述懐する。
「回々教(ここではイスラーム教のことを指す)なるものがいかに偉大な勢力を持っているかということを思うたのであります。現に自分らがうろついたシナ・トルキスタンや、ロシア・トルキスタンや、それからペルシア、小アジア、アフリカの東海岸に渡り、なおまたロシア領内の全トルコ人種がことごとく回々教徒で社会に非常な勢力を持っているということについては、多少この方面に向かってなんらかの事業を試みようとする人々に対しては、よほどの注意を払わなければならないと思います。」(中亜探検)
近世に活躍したタタールスタン出身のムスリムジャーナリスト、イブラヒムが伊藤博文との対面時に話した内容は、客観的にみても現代にも通底している様に思える。
「欧米列強はイスラームの精神的な力に等に気づいています。政治的な力にしても、それを支えるのは宗教です。より正確には、大砲よりも、銃よりも、装甲艦よりも、大型戦艦よりも強い武器があるとすれば、それこそ宗教なのです。(中略)そこで宗教の力を(資本主義自由社会の)自分たちの政治に役立てようと、イスラームを常に悪であり敵とみなし、世論をその方向へ導く。列強の考え方、政策は全てこれに尽きるのです。」(小松久男『イブラヒム、日本への旅』より)
同じく、同著で小松氏は以下のようにイスラームが広域に広がる過程を説明している。
周知のように、イスラームは預言者ムハンマドがアラビア半島のメッカで神の啓示を受けたことに始まる。この清新な宗教を報じたアラブは、またたくまのうちに当時の二大大国であるビザンツ(東ローマ)帝国とササン朝ペルシアの領土を席巻して、巨大なイスラームの文明を築き上げた。古代文明の精髄を継承し、陸上と海上の主要な通商路を押さえた帝国は、その豊かで進んだ経済と文化によって同時代の世界に置ける文明の中心となった。
アラブムスリム軍はムハンマドの没した7世紀には早くもカフカース山脈を越えて現在のダゲスタン地方まで侵入する一方、同じ7世紀末には中央アジア南部のオアシス地域の様子を伺うに至った。通商の達人ソグド人などイラン系の人々が住むブハラやサマルカンドなどのオアシス都市をアラブ軍が征服するのは八世紀はじめである。オアシス住民に受容されたイスラームは、やがて中央ユーラシアの大草原に展開するトルコ系遊牧民の間にも着実に浸透していった。これらの都市は、やがてイスラーム教学の中心地となり、とりわけイスラームの神学や法学の伝統を育んだブハラは中央ユーラシアにおいて「聖なるブハラ」の令名を取ることになる。
そして10世紀に入ると、イスラームはヴォルガ川中流域にも多くの信者を得た。トルコ系ブルガールの王が、同じトルコ系ながらユダヤ教を信奉する遊牧民国家ハザルの支配から脱し、経済的な発展を図るためにイスラームの受容を決意したからである。ブルガール王の要請をうけて、時のアッバース朝カリフは使節団をはるか北方に派遣する。921年6月バクダッドを発った使節団はおよそ一年後にブルガールに到着した。幸いなことにこの使節団の中にいたイブン・ファドラーンが自らの見聞をアラビア語の旅行記に残している。
道中で彼が出会ったトルコ系諸族は形ばかりのイスラームを受け入れたに過ぎず、また異教の慣習も色濃く残していた。イブンファドラーンは言う。「私は、彼らが「アッラーの他に神なし」を唱えているのを聞いたが、それとて格別、その文句を信じているのではなく、彼らのところを通るイスラーム教徒に近づかんがため、ただその言葉を口にするだけなのである」と。
さらに、ヴォルガ側でみたルース(ロシア人)といえば、完璧な体格を持ちながら「アッラーの創造されたる者の中でもっとも不潔な人々であって、大便や小便の後始末はもちろんのこと、男女の営みの後にも身体を清めようとしない。ましてや食事のときに手を洗うことはなく、まるで彷徨い歩く野生のロバのようで」あった(以上の引用は家島彦一訳による)。バクダードの洗練された都市文化になじんでいたイブンファドラーンから見ると、トルコ系諸族もロシア人も「野蛮人」に見えたのであろう。
しかし、イスラームを受け入れたブルガール王国は北ヨーロッパと中央アジア、西アジアとを結ぶ通商の要所を押さえて発展していった。隣接する森林地帯からもたらされる毛皮は、王国の重要な商品であった。今でもヴォルガ側湖畔にはブルガールのイスラーム文化の面影を伝える遺跡(ブルガール遺跡)が残されている。王国は、13世紀にモンゴルの攻撃を受けて崩壊し、この地のムスリムは異教徒の支配下に入った。モンゴル人たちは領土を支配し、文化が混交したものの、やがて言語的にトルコ語化し、宗教としてもイスラームを受容するようになっていった。モンゴル帝国は、ロシアの諸侯を臣属させたばかりではない。それはヴォルガ中流域からクリミア半島に及ぶ広大な地域のトルコ化とイスラーム化を結果的にもたらしたのである。
このような中央ユーラシアの歴史舞台にロシアが主人公として登場するのは、ようやく16世紀になってからのことだった。その画期をなしたのは、雷帝の名前で知られるイヴァン四世(在位1533~84)が、ちょうどブルガル王国の故地を占めていたモンゴル帝国の継承国家の一つ、カザン・ハン国を1552年に征服した事件である。これは、ロシア人がタタールと呼んだ異民族を従えることによって、ロシアが多民族他宗教帝国へと変容する出発点になっただけではない。イスラームを信仰する集団、すなわちタタール・ムスリムを初めて支配下に組み入れた臣民という点でも注目に値すべき事件であった。
はるか南では、オスマン帝国がスレイマン一世の統治下に空前の繁栄を享受しているときに、ヴォルガ川中流域のタタール・ムスリムはロシア正教を奉じるツァーリ(皇帝)の臣民となったのである。今日もモスクワの赤の広場を彩るヴァシーリー大聖堂は、カザン征服という戦勝記念の建築物にほかならない。
以後、陸の帝国ロシアは、クリミア半島、カフカース、西シベリア、カザフ草原、中央アジアなど、ムスリムが多く住む地域を3世紀以上の年月をかけて版図に加えていくことになる。20世紀の初頭、帝国内のムスリムはおよそ2000万人、総人口の約13%と推定されている。それは同世代のイスラーム大国、オスマン帝国のムスリム人口よりも多かった。ロシアはロシア正教についで巨大なムスリム人口を持つ多民族国家だったことを確認しておこう。
イヴァン雷帝にはじまり、歴代のツァーリがムスリムにとってとった行動は概して抑圧的であった。ロシア帝国の建設者とも言われるヨーロッパ大好き帝王ピョートル一世は、それまでのイスラームの信仰を保持していたまま出仕していたムスリム・エリート(軍務タタール)に改宗をせまり、女帝エリザヴェータ・ペテロヴナ治世の1744年にはカザン県に536を数えたモスクのうち、実に418が破壊されてしまった。モスクが残されたのは、ロシア人も新たに改宗した正教徒もいない農村に限られた。ロシア正教への改宗は、宣教活動にとどまらず、税や徴兵、時には刑罰の免除などの特典を与える行政的な措置によっても推進された。
こうした中でロシア正教に改宗した人々はクリャシェン(ロシア語の「洗礼を受けた者」から派生した呼称)と呼ばれ、ムスリム社会とは別個の共同体を形成した。もっとも、中には外見は改宗を装いながらイスラームへの信仰を内に秘めた「隠れムスリーム」も少なくなかった。何れにしても長くロシアの統治下におかれたヴォルガ・ウラル地方は、父祖の信仰を捨ててキリスト教徒に改宗する集団が生まれたという意味で、イスラームの長い歴史の中でも稀な事例を提供している。のちにロシアの東洋学者バルトリドは、「ロシア領内のムスリムの状況は多くの点でオスマン帝国内のキリスト教徒よりも劣悪だった」と指摘している(イスラームの場合は、同じ一神教のルーツから生まれた「啓典の民」としてキリスト教徒、ユダヤ教徒は異宗教の税金を払えばそのまま自身の宗教を保護していた)。改宗はもとより、
居住・職業の制限やロシア人の植民などによって生存を脅かされたムスリムはしばしばウラル以東の辺境やオスマン帝国に移住し、ヴォルガ・ウラル地方の農民反乱には宗教の別を超えてムスリムも少なからず参加していた。
以上は前のブログで紹介した、以下のタタール人のムスリムジャーナリストであるイブラヒムについて書いた本より引用したものだ。
こういったロシアの締め付けは、冒頭の「野蛮な未開人」であったことへのコンプレックスの裏返しといってもいいと個人的には思う。ピョートル大帝のヨーロッパへの憧れは、一度はアラビアの使節団に野蛮な未開人と思われた自分たちに「高貴さと優雅さ」を求める葛藤であり、更に言えば、それらをバカにしたアラビアのイスラーム文明が発達したのも、元はと言えば未開の砂漠の野蛮人でしかなかったアラビア人がそのコンプレックスをエジプトやビザンツ、ペルシアなどの文明国への侵略とその文化を受容し洗練されていくと言う過程でちゃんと経験しているのである。早い話が「憧れの裏返しで徹底的にいじめる」ということなのだ。
ヨーロッパの歴史家には大陸の東の端であるロシアを西の端であるスペインと比べるものが少なくないと言う。歴史的にどちらもイスラームという強烈な個性を持つ大きな世界と対峙して、ヨーロッパのキリスト教世界を「野蛮な異教徒」から守った最前線だからである。とくにロシアは数世紀にもおよぶ英雄的な戦いの中で疲労困憊したが、その聖戦士たちの戦いは無駄ではなかった。というのは、ロシア人が東で盾となったヨーロッパはイスラムやモンゴルの侵略から救われてヨーロッパ近世の輝かしい文明を発展させられたからだというのである。しかし、この犠牲の代償はすくなくなかった。スペインのイスラム征服者とは違って、ロシアのモンゴルやイスラームは少しでも積極的な役に立つ遺産を残したとは言えないとされる。プーシキンはこう嘆いたという。「タタール人はムーア人(スペインのムスリム)とは違っていた。そのロシア征服は、代数もアリストテレスももたらさなかった。」それどころか、モンゴルやイスラームによる抑圧、いわゆる「タタールのくびき」におかれたロシア人は「アジアの野蛮人」を打ち負かして生き延びるためには、敵のやり方を学ぶ必要があった。こうしてモスクワのロシア人たちは、皇帝専制、残虐な施政、農奴制、自由の欠如など、その後のロシア帝国の悪しき遺産になる特徴を敵から受け継いだというのである。こうした考えは、ロシア帝国からソビエト連邦に至るほとんど全ての文学や歴史作品に書き込まれたイメージだと言って良い。こうしてロシア人はあたかも自分たちが、他のどの民族にも増して(イスラームの野蛮な手から世界を救った)守護者と救世主の役割を果たしたという自負が強い。ロシア人に見られる独特な感慨は、彼ら自身にある種のメシア的な使命感を与えた。それは弱々しいヨーロッパ人の弟たちを野蛮で未開なアジア人の侵略から守り、更に進んで「野蛮なアジア人」をしかるべく文明化するということであった。
(中略)
しかし事実はまるで逆であったのは、先ほどのイブン・ファドラーンの旅行記の内容からも想像がたやすい。ロシア人の祖先たちが9世紀にアジアと初めて接触した時に未開だったのは、むしろほかならぬロシア人の方であった。もし10世紀初頭にかつてのソ連にあたる領土の中で文明と未開の世界を切り離す線を引こうとしたら、それはロシア人はじめスラブ系民族の多い土地と、ムスリム系民族が住んでいる地域の境目になるだろう。ヴォルガ川中下流域からカフカース山系を通ってカスピ海へ出てシムダリヤ川に抜ける線がそうである。この線に接する地域は、ちょうど今現在の民族・領土問題で失業率が高く、平均収入もロシアと比較して低い各共和国に相当する。14世紀半ばになってさえ、ロシア人たちの住む北辺は『世界三大周遊記』の作者であるイブン・バットゥータが名付けたように、中東に住む多くのムスリムにとっては「ズルマ(闇黒)の地」に過ぎなかった。
ここまでが、『ラディカルヒストリー』からの引用であるが、歴史というのがいかに後から政治や体制のイメージ戦略に操作されているかという点でも興味深い話である。イスラームに関する話は、私たちが戦後から欧米メディアや歴史教育を通じて普段常識だと思っていることの裏側を意識させられるものが多い。(日本においても古くからの歴史書にもそういった筆者の立場と目線を感じることは多いし、古今東西そういうものなのかもしれない。)
しかし、これらの経緯を踏まえて国の体制の中で大いにムスリムなどの異教徒や、大黒屋光太夫などの漂流民や移民の力をフル活用して国を発展させていくのがエカテリーナ二世であり、その頃に拠点を置いたサンクトペテルブルクは発展していくのである。
そう言った流れで、タタールスタンのボルガール→カザン→モスクワ(カザン大聖堂と戦勝圧政)→サンクトペテルブルグ(容認と発展)と旅をすると、リアリティが急に湧いてきて見るもの聞くもの全てにテンションがあがるのである。
サンクトペテルブルクのエカちゃんに続きます!