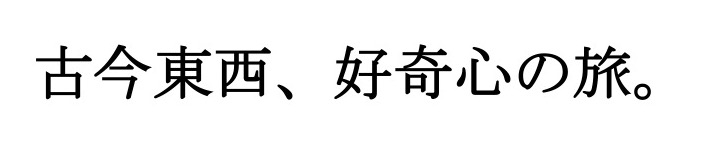【BOOK】どうしたら人は「退屈」を跳ね除ける暮らしができるのか

人間はなぜ「暇」を持て余し、「退屈」するようになったのか、そして、そもそも「退屈」とはなんなのか?そして、「退屈」しない暮らしをするためにはどうしたらいいのか? ということを歴史的・哲学的に考察した一冊が「暇と退屈の倫理学」である。ここしばらく読んだ本の中でも面白い。
目次
「暇」とは何か
そもそも「暇」と言う概念は、「労働効率化の副産物」であり、新しい消費市場として作られたものである、と言うのが以下だ。
現在では「労働」までもが消費の対象になっている。労働はいまや「忙しさ」という価値を消費する行為になっているのだ。一日に十五時間も働くことが自分の義務だと考え、それをテレたような、自己満足したような顔でしゃべっている社長や重役の「わざとらしい」忙しさがいい例である。労働が消費されるようになると、今度は労働外の時間、つまり余暇も消費の対象になる。自分が余暇において、まっとうな意味や観念を消費していることを示さなければならないのである。「自分は余暇を自由に消費できるのだぞ」といった証拠を提示することをだれもが催促されている。だから余暇は、もはや活動が停止する時間ではない。それは「非生産的活動を消費する」時間である。何かをしなければならないのが「余暇」という時間なのだ。
搾取される現代の「暇」
資本主義によって、少なくとも先進国の人々は裕福になった。そして余暇という暇を得た。しかし人々は、その暇をどう使ってよいのか分からなくなっている。何が楽しいのかが分からなくなっている。自分の本当に好きなことが何なのか分からない。そこに文化産業がつけ込む。土曜日のテレビは翌日の日曜日に時間と金を使ってもらう娯楽の宣伝番組を放送する。文化産業が、自分たちが作った既成の楽しみ、産業に都合のいい楽しみを人々に提供する。
かつては労働者の労働力が搾取されていると盛んに言われたが、いまではむしろ労働者の余暇が搾取されている。高度情報化社会という言葉すらが死語になりつつあるいま、この暇の搾取は現代の資本主義を牽引する大きな力である。
なぜ暇は搾取されるのだろうか。それは人が「退屈」を嫌うからである。人は暇を得たが、暇を何に使えばよいのか分からない。このままでは暇の中で退屈してしまう。だから、与えられた楽しみ、準備・用意された流行や快楽に容易に身をゆだねる。しかし、その「用意された快楽」から一時的な気晴らしを得るものの、根本的な退屈が満たされることにはならない。
では、そもそも何故退屈なのだろうか?
「退屈」が起きる瞬間
「人間は考える葦である〜」の『パンセ』で有名なパスカル曰く、「人間の不幸などというものは、どれも人間が部屋にじっとしていられないがために起こる。部屋でじっとしていればいいのに、そうできない。そのために、わざわざ自分で不幸を招いている。」(中略)私たちは普段、精神的・身体的な負荷を避けるために、様々な工夫を凝らして生きている。例えば、長いこと歩いて疲れるのを避けるために自動車を発明して乗る。だが、退屈すると、あるいは退屈を避けるために人はわざわざ負荷や苦しみを求める。つまり、パスカルの言う「部屋の中でじっとしていられず、退屈に耐えられず、気晴らしを求めてしまう」不幸な人間とは、「苦しみを求める」人間のことに他ならない。(中略)苦しむことはもちろん苦しい。しかし、自分を行為に駆り立ててくれる動機がないこと、それはもっと苦しいのだ。何をして良いのかわからないというこの退屈の苦しみ。それから逃れ、自分が行動へ移るための理由を与えてもらうためならば、人は喜んで苦しむ。
と「生きがいを全うする苦しみ」を求めていると。
まあ、これがいわゆる「救済活動」としての宗教となったり、「大義名分」としての戦争につながったり、「目くらましとしての仮想敵をあてがわれる」ことになったりつながってくると思われる。また、原理主義やテロの概念にも通じるところがあるように思われる。それぐらい人は自分の使命と、その使命に対する生きがいを見出したい。何もすることがない状態に耐えられない。それは大きな喪失であるのだ。そして現代社会においては、表面的な平和、産業の成熟、そしてそれらの結果である生活の安定に直面した人々の多くが、“生きている”という感覚の欠如に苦しみ、“打ち込む”こと、“没頭する”ことを渇望している、と言う。
いつから人間は「退屈」になったのか
では、人は一体いつから何もすることがない状態が耐えられなくなった(=退屈してしまう)のだろうか。
その答えをこの本では「人間が遊動生活をやめ、定住生活を始めるようになったことで、退屈を回避する必要に迫られるようになった」と言っている。
遊動生活では移動のたびに新しい環境に対応せねばならない。新しいキャンプ地で人は五感を研ぎ澄ませ、水や食料のありか、薪はどこで取れるか、危険な獣はいないかと散策する。こうして新しい環境に適応しようとする中で「人の持つ優れた探索能力は強く活性化され、十分に働くことができる。新鮮な感覚によって集められた情報は、巨大な脳の無数の神経細胞を激しく駆け巡る。」
だが、定住者がいつも見る変わらぬ風景は、感覚を刺激する力を次第に失っていく。人間はその優れた探索能力を発揮する場面を失っていく。だから定住者は行き場をなくした己の探索能力を集中させ、大脳に適度な負荷をもたらす別の場面を求めなければならない。
こう考えると、定住以後の人間が、なぜあれほどまでに高度な工芸技術や政治経済システム、宗教体系や芸能などを発展させてきたのかも、合点が行く。人間は自らの有り余る心理能力を吸収する様々な装置や場面を自らの手で創り上げてきたのである。(中略) 定住民は、物理的な空間を「移動」しない。だから自分たちの心理的な空間を拡大し、複雑化し、その中を「移動」することで、もてる能力を適度にはたらせる。したがって、「退屈を回避する場面を用意することは、定住生活を維持する重要条件であるとともに、それはまた、その後の人類史の異質な展開をもたらす原動力として働いてきたのである。」。それが、いわゆる「文明」の発生である。
ちなみに、トイレやお墓の概念が生まれたのも「定住」を始めるようになったからと言うことだ。さらに、子供の頃にトイレを覚えることがなかなかできないのは、遊動生活の名残であると。遊動生活をしていた頃は、固定された場所にトイレやお墓を作る必要もなく、さらに毎日が環境の変化ばかりで常に最大限の探索能力を発揮し続けなければならないので探索を止めて退屈する暇がないが、定住生活を始めると次第に生活そのものがパッケージ化されていき、物事を新たに探索することができなくなって「退屈」と言うものが生まれてくる。そんな状態を回避するために、芸術や文化に探索能力を集中させた結果、文明が花開いたと言う話である。これを踏まえると、全体的な文明が限界まで成熟している今、なぜ人々がノマドワーカーに憧れ、生活の流動化(モバイル化)をさせようという動きにあるのかも理解できる。芸術や文化への探索能力を発揮できない以上、動くことで「探索能力」を使っていくしかないからだ。そしてそれもできない場合、得体の知れない「退屈」な「与えられた享楽」に甘んじるしかない。
動物と比べて、なぜ人間は退屈するのか
すべての生物はそれぞれの「環世界」を生きている。環世界とは「その生物種にとっては必要かつ十分な要素が備わった、その生物種だけの宇宙=時間」のことである。たとえばダニの環世界は、自分が寄生する哺乳動物の酪酸のにおい、摂氏三七度の温度、体毛の少ない皮膚組織 のわずか三つのシグナルだけで成り立っている。それ以外のものはダニにとって存在していない。
ドイツ・ロストックの動物学研究所には、一八年間も絶食して三つのシグナルが揃うのを「待っている」ダニが、生きたまま保存されているという。そんなに長いあいだ、三つのシグナルが揃うのをひたすら待つことは、人間には驚きである。(中略) 私たちが、「ダニは一八年間も絶食して待つ」事実に驚くのは、ダニも人間と同じ時間を生きていると前提してしまっているからだ。「環世界」の概念を発見したエストニア出身の理論生物学者ユクスキュルは、ダニはその待機時間中、一種の冬眠状態にあると推測している。それは何年も続く。そして哺乳動物の酪酸のシグナルがくるや否や、その冬眠は解除され、三七度の動物体目指して木の枝から落下し、すがりついた皮膚の中でも体毛の少ない部分に、まっしぐらに進むのである。(中略) これまでは、時間は客観的に1つの固定されたものであるとされ、固定された時間なしに生きる主体はありえないと言われてきた。しかしそうではない。ダニも、カタツムリも、犬も、そして人間も、その独自の時間を持っている。いまや「それぞれの生物種ごとの時間」以外に、「時間」はありえないと言わねばならない。(中略) ただ、人間はその他の動物と比べて比較的容易に別の「環世界」へと移動することができる。これが人間と動物との違いだ。逆に言うと、人間は一つの「環世界」にひたすら浸っていられない。これが人間が極度に退屈に悩まされる存在である理由がある。何か特定の対象の「環世界」に<取りさらわれ>続けることができるなら、人間は退屈しない。しかし、人間は容易に他の対象に<取りさらわれる>のだ。つまり、人間は環世界を相当な自由を持って移動できるからこそ退屈するのである。
物を探索する、考えるとはどう言うことか
フロイトは、人間の精神生活はあらゆる面において「快」を求める原理によって支配されていると言っている。人間の精神、正確に言えば無意識は、快を求め不快を避ける、と。ここに言われる「快」とは、「快楽」という言葉がさすような激しい興奮状態のことではない。その正反対である。基本的に、生物は「自らを一定の状態に保てること=習慣」が「快」である。だが、快原理による説明は生物全般の一般的傾向としては正しいのだろうが、人間についてはさらに説明を追加しなければならない。なぜなら、この快は退屈という不快を否応なしに生み出すからである。 人間は習慣を作り出すことを強いられている。そうでなければ快に生きていけない。だが、習慣を作り出すと、その中で退屈という不快を生み出してしまう。
人は習慣を創造し、新しい環世界を獲得していく。そうすることで周囲を「自分に分かりやすいシグナルの体系」へと変換する。なぜそうするのかといえば、当人がものをできるだけ考えないですむように生きていくためである。四六時中まったく新しいものに出会って、そのたびに深刻に考えていては、人は生きていけない。
人がものを考えざるを得ないのは、作り上げてきた環世界に変化が起きたときである。何か新しい要素が「不法侵入」してきてそれまでの習慣の変更を迫られる、そうしたときである。何ごとも考えないで済むように環世界を構築してきた人間としては、そのような「不法侵入」はショックであろう。ものを考えるとは、それまで自分の生を導いてくれていた習慣が多少とも破壊される過程と切り離せない。考えるとは何かによって<取りさらわれる>ことだ。その時、人はその対象によってもたらされた新らしい環世界に浸る他なくなる。
退屈の魔力から逃れる方法
これらの解決策として、具体的に結論として書かれていることの一つが「贅沢を取り戻すこと」だ。
贅沢とは浪費することであり、浪費は物を過剰に受け取ることなので、そこで受け取れるものには物理的な限界があり、どこかでストップする。そこに現れる状態が満足であり、豊かさである。それに対して、消費は物ではなくて「最新」や「流行」などの観念を対象としているから、いつまでも終わらない。終わらないし、満足も得られないから、満足を求めてさらに消費が継続され、次第に過激化する。満足したいのに、満足を求めて消費すればするほど、満足が遠のく。そこに退屈が現れる。これこそが現代の消費社会によって引き起こされる退屈の姿である。消費行動においては、人は物を受け取らない。だから消費が延々と続く。ならば、浪費において物を受け取れるようにするしかない。物を受け取ること、それこそが贅沢への道を開く。しかし、そこには課題がある。ここで言う「物を受け取ること」は、すなわち、「自らその物事を楽しむこと」である。例えば、衣食住のような日常のことや、芸術文化、娯楽、歴史などを楽しむことである。しかし、楽しむためには準備が不可欠であり、楽しめるようになるためには訓練が必要なのである。
こういったことが非常に上手なのはかつての「有閑階級」の人々だ。彼らは浪費の限りを尽くした裕福な身分であり、「暇」もたくさんある。しかし、彼らは音楽や芸術、詩や学問などを幼い頃から鍛えているので、楽しみ方を知っている。そうすると、日々において「退屈」することがない。
人は決断して奴隷状態に陥るなら、思考を強制するものを受け取れない。しかし、退屈を時折感じつつも、ものを享受する生活の中ではそうしたものを受け取る余裕を持つ。これはつまり、「楽しむことは思考することにつながる」と言うことである。なぜなら、楽しむことも思考することも、どちらも「受け取る」ことであるからだ。人は楽しみを知っている時、思考に対して心が開かれている。しかも、楽しむためには訓練が必要なのであった。その訓練は物を受け取れる能力を拡張する。これは思考を強制するものを受け取る訓練となる。そういった訓練を重ねることで、人は楽しみ、面白がることを学びながら、ものを考えることができるようになっていくのだ。
これが「実学」分野の弱いところだ。現代のある程度安定した生活を送っている人々が、「今こそ「教養」を身につけるべきだ」と無意識な危機感を持っているのも、「退屈」と戦う術、「既成の社会構造の中に取り込まれることなく、自身で考える、生きる力を取り戻す」ためであるとも考えられる。そのための、「楽しみ方を訓練する」のである。
「楽しみ方を訓練する」と言うのは、「畑を作る」ことと似ている。年月をかけて様々な物事や物の見方を吸収し、様々なタネや、それらが育った花、育たなかった花などを試行錯誤の結果インプットしながら良い土壌を整えていくことが大事だ。そうすることで、小さなタネからさらに大きく見事な花をたくさん咲かせることができる。それらが武器となり、同じ世界の出来事を見たり経験しても、得られるものがぐんと増える。得られるものが増える、と言うことは、既存の自分(の世界)と物事(の世界)の接点が増えると言うことだ。それは紛れもなく「自分事」である。人は、「自分の世界観」について言われていることに対しては、必ず共感し、興味を持つ。興味を持って物事と「自分の世界観」の接点を広げることについて「考える」と楽しい。夢中になる。だから、どんどん網の目のように広がっていく。「教養」を身につけると言うことは、その「自分の世界観」の網を最大限に強くし、最大限に広く引き延ばすと言うことだ。だから、同じ経験をしても鍛錬していない人よりも「受け取る」ものが格段に増えるのだ。そして、この過程こそが「物事を自主的に探求し、理解する」プロセスとも言える。
この「楽しむことができる力」が、器用貧乏の私が文句なく自分に誇れる強みであり、生きる支えである。だから、私はここで言う「退屈」をすることがほとんどない。
そして、この「楽しむことができる力」を伸ばす秘訣は、たった一つの約束を守り通すことだけであり、実際私が物心ついた頃からずっと取り組み続けてきたことである。が、それについてはまたブックレビューとは別に時期を改めて述べたいと思う。
それはそれとして、この本ではまだまだ多くの観点から考察されていたが、やむなく割愛したところが多いのと、全体を読んでこそ腹落ちがする部分があるので、是非この記事を読んでくださった方には、本を通しで読んでみていただきたい。それによって、「何も不自由がないはずなのに何故か退屈な日常」から抜け出したい人、「退屈から抜け出しているがさらに楽しみたい人」の一助になったら嬉しい。