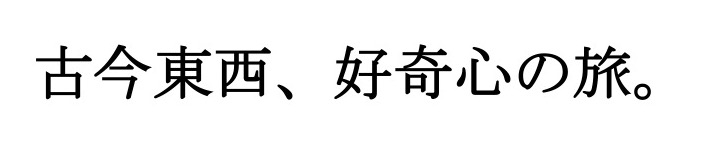【BOOK】ニッポンのムスリムが自爆する時〜日本とイスラームの関係性〜
イスラーム教に関する新しい視点を日本の読者に得てもらうことを目的とした試金石としてこのエッセイは書かれている。
そのため、神学や文学、翻訳、日本とイスラム教の関係などそれぞれの文化的な主題を取り扱っており、直接的に「テロ」の問題を取り上げているわけではない。
それにしても、久々にかなりパンチの効いた読み応えのある本に出会った。
タイトルだけだと、手に取ることを躊躇すると思う。
しかし内容は至って冷静だ。
そして表紙や中身には可愛い女の子が描かれていて、タイトルとのギャップが激しい。
そして、非常に現代のムスリムと彼らを取り巻く環境について、自分ごととして丁寧に書かれている。
目次
知られていない日本との深い関係
この本を偶然手にするまで、私は全然その重要な事実に気づいていなかった。
東京都府中市にある、多摩霊園という公営墓地をご存知だろうか。
私も府中市住まいが長く、免許更新などの際には近くを通り過ぎていた。
多摩霊園は日本で初めて造られた公園墓地である。この種の墓地の建設は、仏教から距離をとった明治政府による新国家建設の過程で求められた事業だった。(中略)現在、霊園の面積は128万237平方キロメートルと広大で、40万を超える人々が埋葬されている。著名人の墓も多い。特別区画として設けられた名誉霊域には、東郷平八郎、山本五十六、古賀峯一(いずれも海軍大将)三名の墓がある。その他、高橋是清や西園寺公望といった政治家、与謝野晶子や三島由紀夫といった歌人や小説家、その他実業家、芸術家など、霊園のあちこちに各界の著名人が眠っている。多摩霊園は単に日本の公園墓地建築を代表するというだけでなく、明治以降、近代日本が歩んだ歴史の一端を記憶する施設であると言える。この霊園の正面入り口から見て斜め右の方向に少し歩いたところに外人墓地という区画がある。宗教や国を基準にいくつかの墓のまとまりが作られていて、十字のついたキリスト教の墓や、中国風の墓が目立つ。この「外人墓地」の一角にムスリムの墓が並ぶ場所がある。墓の数は100を超えない程度で、簡素な作りの者が多い。土葬のために各々広めに設けられた土の上に、アラビア語、トルコ語、英語、日本語などさまざまな言語の書かれた墓石や立札が添えられている。埋没者はチュルク系が多が、中国人や日本人もいる。
これら一群の墓の、一番奥の列の中ほどに、アブデュルレシト・イブラヒムという人物が眠っている。
これを読んだ私は一瞬、我が目を疑った。
以前、私は日本とタタールの大東亜共栄圏を巡る政治的協調関係と、大好きな東京代々木モスクの説明をするために、アブデュルレシト・イブラヒムという人物について書いていたのだ。
ええええええええええええええええええええええ!?
タタール人のイブラヒムさんが、こんなに身近にいたなんて!!!!
なぜ、どうして府中に住んでいる間に気づけなかったのだろうか。
わざわざ、ロシアのタタールスタン共和国にまで行ったのに!!!
こんな身近なことに気がつかないとは耄碌したものだ。
図書館で借りているとはいえ、この出だしだけで、すでに本十冊分の値打ちがある。
イブラヒムじいさんについては詳しくは上記の私の記事を読んでもらいたいのだが、
1857年にロシア帝国領に生まれたタタール人ウラマーで、世界を股にかけて活動した汎イスラーム主義者であり、世界中のムスリム文化圏に日本が良い国だと印象付けた、著名なイスラムジャーナリストでもあった。今日、イスラム文化圏の人々が大体において日本人に対して良い印象を抱いてくれているのは、この御仁の力によるものと言っても過言では無い。明治時代に日本に滞在し、伊藤博文など政界の著名人と次々謁見を実現し、イスラームの可能性を説いた。そのほかに世界中を旅する旅行家でもあり、ロシアのタタールスタンのムスリムへの締め付けに対する革命家でもあった。
「イブラヒム翁、府中に有り」
これは私にとって衝撃な事実であった。次回、必ず訪れなければならない。
イブラヒムという人物を忘れ去ることは、日本とイスラーム教関係史の、ある重要な局面を忘れ去ることも同時に意味している。(中略)日本人は、世界中のムスリムにジハードを促し、日本が戦う「聖戦」への参加を呼びかけた。また実際に多くのムスリムを統治下に置き、戦争に動員した。そしてイブラヒムのように、日本に協力しようとする汎イスラーム主義者の活動も存在したのである。戦後の日本社会は、この邂逅の事実をもはや記憶していない。
しかし、武蔵野の大地の苔むした墓の中に、その記憶は残り続けている。
満州国の五十万、支那の三千万、東印度の五千万、此島の五十万、秦の五十万のイスラム教徒と手に手をとって吾が国が、イスラム教徒覚醒運動史上におけるこの伝統をさらに発展させ、ただに東亜のみならず、世界イスラム教徒の圧制者たる英国打撃の大業に邁進する義務と決意とを有することは言うまでも無い。問題は、この日本の決意を掬み、これに協力する世界イスラム教徒の覚悟にある。吾等は世界三億のイスラム教徒がイブラーヒーム翁の檄に応え、その強烈無比なる信仰を武力化し、諸君の頭上に君臨する不審者英国ならびにその共犯米国に対し、コーランの教える如く 「汝らやがて打ち破らるべし、地獄へ追わるべし」と叫んで躍起せんことを庶幾して止まないものである。ーーーーーーー『読売新聞』1944年4月26日 社説「世界のイスラム教徒奮起せよ!」
アクチュアリティからの逃避としての日本のイスラム文学
柳瀬によれば、日本には戦前より、「<回教>を巡る膨大な言説、ジャーナリズム・交通・技術・歴史・政治・資源などあらゆる分野にいたる広がり」が存在した。にもかかわらず、日本文学者はこの事実をまともな形で表彰してこなかった。同時に、日本人文学研究者は、日本文学におけるイスラーム教の表象のあり方ーあるいはその奇妙な不在ーの問題に「徹底的に無関心」で有り続けた。日本の「複数の戦後」あるいは「複数の戦前」の中に確かに存在した<回教>という問題群を無視する態度を「アクチュアリティからの逃避」として柳瀬氏は批判する。
その戦前の書籍には、さまざまなイスラム関連文学がある中で、仲小路彰『砂漠の光』、宮内寒弥『贋回教徒』『未来』などが取り上げられ、最近では日本のウラマーである中田考のラノベ、『俺の妹がカリフなわけがない!』(通称オレカリ)がある。イブラヒムはかつて日本に「カリフの再興」を見出そうとしていたと言われるが、中田氏のこの本にもカリフ制の必要性と、それにおける日本の役割が見られるような気がしてならない。イスラム教世界とそうでは無い世界のバランスをとるために、いわば指導者をなくして法解釈の多様性を迎えるイスラムの中での未来的秩序を設けるために、カリフ(正統後継者)制を活かすというのは一つの方法であると確かに共感する。そう言うわけで、遊びのように見えて、実は真剣に描かれているのではないかという松山氏の意見は納得できる。
そこには、忘却の彼方となった日本イスラーム史を想起させること、そのための文学の可能性を再び開くことといった隠れた意図があると松山は指摘している。
日本のイスラームにおけるDEI
モスクやイスラーム教団体で決定権をもつムスリムは、マジョリティーから見て扱いやすい、話のわかる、「良いマイノリティー」として自分たちを表象しようと努める。彼らは、「私たちは日本で不自由なく暮らしている」「差別や偏見は感じない」と述べ、「マイクロ・インバリデーション」(無効化)に加担するようなコミュニケーションを促す傾向が強い。そのため、日本社会により少なく順応・包摂されている(ように見える)ムスリムや、日本社会への不満を持つムスリム、実際に偏見や差別に晒されていて、その問題についてのマジョリティー側の責任に言及しかねないムスリム、マジョリティーの目から奇異に映りそうなムスリムを、意識的にではなくとも(実際には意識的であることが多いが)対話の場から遠ざけようする。こうした「サバルタン」の中には、性的マイノリティーのムスリムも含まれる。イスラーム教のより「正統」とみなされている教説は、同性愛者やトランスに対して非神話的である。そのため、日本のムスリムコミュニティーの中で、彼らが自身の性的な問題をオープンに語ることは憚られる。
日本の中の限られたコミュニティの中で暮らしているからこその問題もあるのだ。
新しい文化としてのワールドイスラミックポップ
2000年代から、ピアノやギター、ドラム・セット、シンセサイザーなどを用いた現代洋楽風の曲に、イスラーム教の伝統的な価値や教えを表現する英語の歌詞や、象徴的なMVを合わせる音楽が盛んに発信されるようになった。本エッセイでは、この種の音楽ー英語で歌われ世界的に聴かれているポップス調のイスラーム宗教歌ーを「ワールド・イスラミック・ポップ」ととりあえず呼んでおきたい。ワールド・イスラミック・ポップは、欧米に居住するムスリムのみならず、イスラーム教諸国のムスリムの間でも多くのファンを獲得することに成功した。ヨーロッパを主要な発信源とする、21世紀に確立したイスラーム教における新しい宗教音楽のジャンルであるーあるいは、イスラーム教の新しい宗教文化と言っても良いかもしれない。
ここで先駆けとして取り上げられているのは、サーミー・ユースフというイギリス人の歌い手である。
彼の洋楽風のイスラーム宗教歌は、欧米から中東、東南アジアまで世界各地のムスリムの間に浸透したそうだ。この曲はミリオンセラーとなり、これまでリリースされたアルバムは総計4500万枚を超える売り上げを記録しているという。
スウェーデン人のマーヒル・ゼインも、より大衆性の強い楽曲を提供するワールド・イスラミック・ポップ界の巨人であるそうだ。
アメリカ人のラーエフは、クリスマスソングやマイケルジャクソンの楽曲のイスラミックなカバーを発信する前衛的な取り組みをしている。
イギリス人のハリス・Jは、世代としては前述のアーティストよりも若い。イラン生まれのサーミー、レバノン生まれのマーヒルとは異なり、ハリスは移民ではなく、生粋のロンドン生まれロンドン育ちで有り、イスラム文化圏での居住経験も持たないそうだが、自らを「自覚的なムスリム」であると同時に「生粋の英国人」として捉えている。
曲調にも確かに彼のアイデンティティが表れており、そこにはオリエンタルな旋律はなく、歌詞以外は普通の洋楽である。イスラミックポップに馴染んできた私からすると、なんとも不思議な感覚に陥る。洋楽の旋律の中に当たり前のように「アッサラーム・アレイクム」が混じる。何曲か聴いているうちに、そのみずみずしさから私はすっかりファンになってしまった。
松山氏の言うとおり、ハリス・Jの音楽にはムスリムとしてのアイデンティティと、イギリス人としてのアイデンティティとを矛盾なく両立させた世代の新しい感覚が再現されているように感じる。
現代西洋的な社会に生きる多くのムスリムは、イスラーム教諸国に暮らすことが、自覚的なムスリムであるために必要な条件であるとは確かに考えていないと思う。それは、国や文化とは切り離された、脱地域化する宗教性である。そこに、ムスリムとしてのオーセンティシティがあるのかどうかと問うのはナンセンスであり、それが新たな形のイスラームの一つの現代的な形なのである。
フランス人のミシェル・ウェルベックの『服従』と言う、ヨーロッパにおいてイスラムがメジャーな価値観として定着化していくという小説のように、そこではイスラーム化していくヨーロッパという見方ができると共に、逆にヨーロッパ化していくイスラームとも言える点では、どちらかがどちらかの文化を「乗っ取っている」とは言えず、互いに再構築し合い新たな文化であり信仰の形を築いているのである。
『服従』の本の背景についてもっと知りたいかたはこちら
遅かれ早かれ、日本においても同じような動きが入ってくるかもしれない。